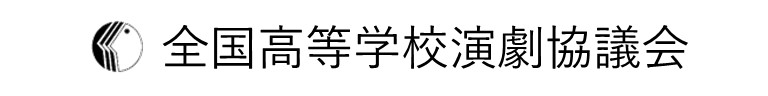本日より、朝更新で行きます。
「本当に・・・」シリーズもみなさんの応援に励まされて、4回目となりました。う~ん、どうなることやら。
③演劇部長Mを一撃のもとに倒した生徒会長は、余裕の笑みを浮かべる時間さえ惜しんで、自宅へ帰るだろう。もちろん勉強のためである。明日は必修英単語100000語のテストがある。範囲は50ページ。生徒会長は、入学以来満点以外取ったことはなかった。余計なことは一秒たりとも考えたくはなかった。少しでも気を抜くと、あれが心に忍び込んで来る・・・。玄関を開け、奥に向かって「ただいま」と声をかけると、一目散に自分の部屋へ駆け上がるだろう。かばんを机において、すぐさま単語集を取り出すと、ベッドに腰掛け、825ページを開くだろう。さすがにここまで来るとアメリカ人も知らないような単語が並ぶだろう。obduracy(頑固)、solipsistic(唯我論)、apostates(背信者)、opprobrium(憎悪)austerity (禁欲) なぜか単語集が自分をからかっているのかのように思うだろう。単語集を閉じてベッドに横になる。
「気合いだ!」「何度やってもダメだな、お前は!」「やめちまえ!」「根性が足りない!」「その場でスクワット100回!」すべての言葉に「!」が付く、体育会系の絶叫が今日も階下から聞こえてくるだろう。生徒会長は、それが聞こえないように別のことを一生懸命考えるだろう。そうだ、楽しいこと、楽しいこと、楽しいこと。だが楽しいことが何も浮かばない自分に愕然とするだろう。
3年前に自宅を改造して作った1階の稽古場で、生徒会長の父、祐一郎はイライラしているだろう。どうして最近の生徒は、気合いが入っていないのか。どうして腹から声を出せないのか。そんなか細い声じゃ、2000人のホールの隅の隅まで声が届かないじゃないか。感情の微妙な、針一本ほどの違いが、審査員に、じゃなかった観客の全員に伝わらなくてはならないのだ。どうしてそれがわからないのだ。スマホだ、スマホのせいだ、絶対スマホに違いない、ととりあえず原因を短絡的に考える祐一郎は、「10分休憩!」と自慢のバリトンの声で部員に伝え、稽古場の隣の自宅のキッチンに入り、ウーロン茶をがぶ飲みするだろう。その間部員たちは、決して休憩することなく、指導されたセリフ「何がお前をここに来させたのだ」を何十回も何百回も、ゆっくり、早く、高く、低く、歩きながら、走りながら、ジャンプしながら、スクワットしながら、エビぞりながら、時にペアで四の地固めをしながら、繰り返すだろう。なぜそのようなことをやっているのか、誰も知らなかった。「そんなことをやって何の意味があるんですか」という質問は、即刻退部を意味した。部員は、高校演劇の強豪校・若柴S高校の演劇部員であった。祐一郎はその演劇部顧問であった。
「何がお前をここに来させたのだ」「何がお前をここに来させたのだ」「何がお前をここに来させたのだ」「何がお前をここに来させたのだ」「何がお前をここに来させたのだ」「何がお前をここに来させたのだ」「何がお前をここに来させたのだ」・・・・・「いい加減にしてよ!」と生徒会長、すなわち祐一郎の一人娘・千春は、単語集を壁に投げつけるだろう。いつもこうだ。稽古中は父の声だけが鳴り響き、休憩中は、演劇部員の同じセリフが連呼された。しかも一人が言っているのではない。37人の部員が一斉に同じセリフを言い続けるのだ。この休憩10分は、稽古場の真上に部屋がある千春にとって耐えがたいものだった。「しかもだ」と千春は、苦々しげに単語集を拾いながらつぶやくだろう。「どうして、『なんでここに来たの、ねえ』と言えないの?」「なぜ翻訳調なの?」確かこれは高校生の友達同士がケンカして、一方が謝りに来る青春ものだった。その謝りに来た相手に「何がお前をここに来させたのだ」はないだろう。しかもそれに続くセリフは「私をここに来させたもの、それはあなたをここに来させたものと同じ」と回りくどいのである。だが、千春は決して父にそれを指摘することはないだろう。中学生の頃まではよく言った。「ねえ、お父さん、それ変じゃない。ふつうの大人の人はそんな言い方しないよ。」父は言った。「ダメだ。書いてあるセリフは、絶対変えてはいかんのだ。一文字でもだ。台本の言葉は作者の命だ、魂だ。それを変えることは、作者への冒涜だ。反逆行為だ。謀反だ!」と台本でよく使われる難しい言葉を羅列し出すので、めんどうくさくなって聞くのをやめた。「結局古いのよね」千春は、自分だったらこのセリフはこう変えるな、という湧き上がってくるアイディアを必死に抑えつつ、単語集に再び集中するだろう。
祐一郎はウーロン茶を3杯連続で一気飲みしても、まだイライラしているだろう。理由はわかっている。部員の芝居が気に入らないのはいつものことだ。あの春の地区発表会。若柴S高校は、最優秀賞を逃したのだ。優秀賞だったのだ。つまり2位と言うことなのだ。そして最優秀をとったのは、ウチの芝居を超えたのが、今まで全く眼中になかったY高だったのだ。これは応えた。娘の学校だからではない。芝居がヘタだったからでもない。ヘタな芝居でも、いいものはある。最近ようやくそれがわかってきたつもりだ。だが、Y高の芝居は・・・まったくわからなかったのだ。ところが観客、つまり生徒や顧問や保護者は大受けなのだ。生徒だけ、若い人だけが受けるのならいい。大人も面白がっている。そこがわからなかった。何が面白いのか全くわからならかった。自分より少し年上であろう、今年演劇部顧問になった、たぶん国語だから一番最後になり手のいない演劇部に当てはめられた、緑が丘C高のP教諭に聞いてみた。「Y高の芝居、わけわかんないんですよね?」P教諭は言った。「いや、確かにわけわかんなかったけどね、私初めて高校演劇ってすごいんだな、と思いました。あ、若柴Sさんの劇もさすがだな、と思いましたけどね。」と明らかに最後の付け加えは社交辞令として言った。なぜならP教諭は、若柴S高の芝居の時、よだれを垂らして寝ていた・・・
「いやあ、春の大会ですからね、いろんな学校が賞をもらうのがいいんじゃないですか。Y高さんもよかったですよ。今までにないアプローチで。ああいうのがこれから高校演劇のあり方を変えていくんではないかなあ。最優秀は納得だな。専門の審査員だったらわかりませんけどね。いや、うちもね、ちょっと生徒主体でやらせてみたんですよ。だから詰めが少し甘かったな。」発表会後の顧問の打ち上げで、祐一郎はいつになく饒舌だった。(続く)
と、とりあえずここまで。これから出かけるので、誤字脱字などは後で校正し直します。