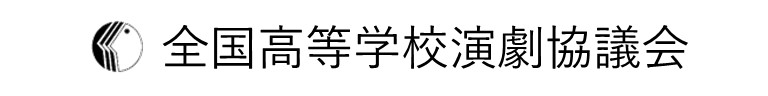夏休みをあと1週間。宿題で追い込まれる時期です。私の宿題「本当に・・・」シリーズも何とか夏休み中にはケリをつけなくてはいけません・・・といいつつ番外編なんて書いてしまいました。前回までのと間があいたので、文体が変わっていたり、設定や名前が違っているかもしれませんが、お気になさらず。
祐一郎は、時計を目にした。午後8時30分。「そろそろだな。生徒も疲れている。」 祐一郎は台本を閉じると、太く響き渡るバリトンの声で「稽古終了」と告げた。結局「何がお前をここに来させたのだ」という一文のセリフを100のバリエーションでやる課題に2時間取り組んできて、一回も「よし」と言われなかった若柴S高校演劇部員26人の目が一瞬輝いた。あと1時間、9時半までこの課題が続くことを覚悟していたのだ。しかしここであからさまにうれしそうな顔をするものはいるはずがない。一人お調子者で、若柴S高校演劇部員に最も似つかわしくない、1年の志保美が「やった!」の「や」を発した瞬間に、部長が足を思いっきり踏みつけた。こういう時はいくら疲れていても「まだやれます」という少し不満げな表情を少し浮かべるのが流儀なのだ。そこで祐一郎が「大丈夫だ。お前らは日本一稽古している。少し休め。」とバリトンの声で言い、部員が「ありがとうございます!」と最後の「す!」が嗚咽で聞き取れないくらいに発するのが流儀なのだ。若柴S高校演劇部の部員は、稽古場を出るまで演劇を続けるのだ。
しかしこの時の祐一郎は違った。足をさする志保美以外、「少し不満げ」な表情を受かべる部員たちに向かってこう伝えた。「5分後に通しをやる。」…目の前が真っ暗になりながらも、当然部員たちは持ちこたえる。「少し嬉しそう」な表情を浮かべるのが流儀だ。「えっ~!」を発する前に志保美の足は部長が踏みつけてある。
祐一郎は、早めに今取り組んでいる劇を仕上げたかった。いや、仕上げるのは無理だ。全体像を見たかった。本当にこの劇で地区大会に臨むのか、いまだ自信が持てないでいた。やはり祐一郎とて「何がお前をここに来させたのだ」のような無生物主語があふれる翻訳超劇に懐疑的であったのだ。だから100のバリーエーションを課題に出し、自分が納得できる言い回しを見つけたかった。しかし見つからなかった…。しかもだ、この劇をやって本当に若柴S高校の劇は変わったことになるだろうか。いや、変わらない。これでは「またいつものパターンね」と言われてしまう。今までは「いつものパターン」でも力で押し切って来た。しかし今は変化球が欲しかった。剛速球の直球ストレートに、カーブやシンカー、50キロの超スローボールを加えたかった。そうしないと、娘の学校の演劇部の舞台には対抗できないのだ。それに稽古場の隅に隠してあるプロジェクタも早く使いたかった。滋賀県で行われる全国大会の前が台本決定のリミットだ・・・。
千春は時々不思議に思う。なぜ若柴S高校の演劇部は常に20人以上の部員をキープしているのだろう。あんなに厳しい部活だ。やり方も古い。それなのに自分が子供の頃から、部員が大量に辞めたなんて話は一度も聞いたことがなかった。辞めるのは、本当に家庭の事情か、転校ぐらいだった。もちろん部員が50人も60人もいる頃に比べれば今は半減である。でも20人~25人というのは高校演劇部にとっては最適な人数だと思う。その理想的な部員数をここ5年ずっと保っている。8人ほどの3年生が抜ければ、8人ほどの新入部員が入ってくる。理想的な演劇部…いや、そんなはずはない。みんな辞めたがっているに決まっている。みんな逃げ出したいのだ。ただ父が怖いのだ。それとも父は催眠術師で、部活に入った瞬間に卒業するまで解けない催眠術をかけてしまうのだろうか。
「ちょ~、信じらんない~」階下の稽古場の外で、これまで父の演劇部にいたことのないタイプの部員・志保美が、同じ1年生の部員に向かって文句を言っていた。「今から通しだってよ。せっかく今日早く終われるかと思ったのに。」「・・・」「あんだけ稽古したんだからみんな疲れてるっていうのがわからないのかな。」「・・・」「それにあたしたち全然出番ないんだから面白くないよね。」「・・・」「もう帰っちゃおうかな~。」「・・・」 従来のタイプの1年生演劇部員に、そのような不規則発言に対応する術はなかった。その時千春は、志保美の信じられない一言を聞いた。「ま、許してやっか、祐一郎かわいいから。」「!!!!!」
時計を見た。72分50秒。初めての通しとしてはいい方だろう。最近まとめるのがうまくなった。しかし反面それは冒険をしないということだ。若いころは夢中になって創っていったら、通しをしてみたら2時間半。それが地区大会1週間前。60分に縮めるのにどんなに苦労したことか。時間と空間をまさに自由に飛び越えさせた。しかしそれが「テンポが良くて小気味いい」と高く評価されて、全国大会まで進んだ。その時、どんなに長い劇も60分以内に、しかも完成された形で収める快感を身につけてしまった。高校演劇的時間感覚・・・プロの芝居を観に行っても、60分を超えるとそわそわし、早く結末を知りたがる。
最近は、大会用作品は57分20秒±5秒に収めるように決めている。58分30秒はダメ、56分20秒もダメ、59分50秒などもっての他である。57分20秒±5秒が上演校的にも、観客的にも、そして審査員的にもベストな上演時間なのだ。長過ぎず、短過ぎず、過不足なく。大会前の通し5回は、ほぼこの時間に収まる。収まらない時は、即反省会及び台本点検である。「その日その日の役者やスタッフの調子によって時間は変わるんですよ。それが芝居ですよ。生き物ですから。」なんて理由は若柴S高校演劇部では通用しない。台本のセリフには通し番号を打ってある。セリフとセリフの間に取るべき「間」を表す記号が打ってある。この記号こそ「若柴S高校の芝居を若柴S高校の芝居たらしめる」門外不出の記号であった。(と、いつの間にか部員間で伝説化してしまった) その台本と撮ったビデオを照らし合わせ、通し時間が延びた、あるいは短くなった原因を徹底的に追及するのだ。そしてそれは時に深夜まで続いた・・・
よく観客の笑いが収まるのを待っていたら上演時間が延びたとか、受けの間を取らないがために、その後の肝心なセリフが聞き取れないということがあるが、それも若柴S高校演劇部にはあり得なかった。ちゃんと台本に「笑い」に対する間の時間が書きこまれているのだ。実際はもっと細かいのだが、大雑把に言うと、笑いは「小笑い」「中笑い」「大笑い」の3段階に分かれていて、それぞれ「1秒」「2秒」「3秒」の間が与えられている。面白いセリフの後には、絵文字で笑いのそれぞれの笑顔が書きこまれ、間の時間を表す記号が添えられていた。
5年くらい前までは、その計算が狂うことはなかった。あまりにも面白いセリフが思いついた時には、「大大笑い」の絵文字と5秒もの間を与えた。それがまさにはまった時、これもまた快感であった。観客によってコントロールされる芝居ではなく、観客をコントロールする芝居・・・それが・・・コントロールできなくなった。受けないのである。3秒の間を与えられた「大笑い」のはずのセリフにクスリとも笑いが起きないことが多くなった。受けないと、その分間を詰める訓練をしていない部員たちは、3秒間、ただ立ち尽くすしかなかった。ほぼストップモーションで。妙な間の多い芝居が出来上がる。演劇初心者の緑が丘C高のP教諭は、遠慮なく言った。「いやあ、若柴Sさんの劇は、変な間が多いですな。あれはセリフ忘れてるんですか。」すると、隣にいた、祐一郎の高校演劇界での地位を知っている顧問は、「あれは、セリフの意味を観客とともに考えたいという、新しい演出法じゃないですかね。」と助け舟を出すのであった。祐一郎は「助かった!」と言う表情を浮かべることなく、「最近ヨーロッパの演劇を研究してましてね、観客と役者が時間を共有する実験的なアプローチが注目を集めているんですよ。それを具体化したのが・・・」と延々演劇論を語り出し、P教諭をますます演劇嫌いにさせるのであった。(続く)
*この作品はフィクションであり、 実在の人物・団体などとは一切関係ありません。特に祐一郎のモデルは、特定の人物ではないし、ましてや私であることなど一切ありません。