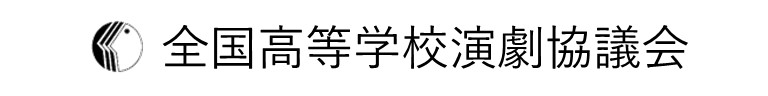全国大会4日前となりました。滋賀大会実行委員長Dang先生は、今日から会館入りしています。私も明日から彦根に入ります。いよいよいよいよいよいよいよ、となってきました。
本日は、昨日に引き続き、滋賀便りです。⑤の続編です。今回も読みごたえがあります。では。
滋賀便り(おうちの演劇観)
「話し言葉」と「書き言葉」の問題に触れた以上、演劇の「台詞」と「身体性」に触れなければならなくなった。演劇が「話し言葉」で成立していることは明らかだが、そこに、歴然とした「身体性」が存在することも当然である。
そこで、「日本人が日本語という言語で演劇をすると言うことがどんな意味を持つのか?」という問題について、話を進めたいと思う。
数年前になるが、米国在住の作家水村美苗が、『日本語が滅びるとき』という評論を出版して話題を呼んだことがあった。その抜粋をしてみる。(かつて図書館教育の発表をしたときに抜き書きしておいたもので、今シコシコとやったものではありません。)少し長いが、我慢して読んで頂きたい。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
水村美苗 『日本語が亡びるとき―英語の世紀の中で―』 (筑摩書房) p302~p307
「表音主義」を中心に据えた戦後の国語教育は、多分に心ある人たちの善意から生まれたものである。日本に生まれれば、どんな人間でも日本語を話すことはできる。ということは、どんなに教育を受ける機会を奪われたとしても、〈書き言葉〉というものを、〈話し言葉〉をそのまま書き表したものだとさえ規定すれば、人は文章を書けるようになる。つまり、「あいうえお」の五十音と最低限の漢字さえ覚えれば、国民すべてが文章を書けるようになる。〈書き言葉〉を、国民すべてのもの一主婦はもちろんのこと、鋤をもった農民や、サイレンの音と共に工場入りをする労働者のものにすることができる。それは、文化の否定どころか、文化を国民すべてのものにしようという文化の礼賛だとかれらは思っていたのであろう。
だが、文化とはそのようなものではない。
国語教育の理想をすべての国民が書けるところに設定したということ、国民全員を〈書く主体〉にしようとしたということ、逆にいえば、国語教育の理想を〈読まれるべき言葉〉を読む国民を育てるところに設定しなかったということである。ところが、文化とは、〈読まれるべき言葉〉を継承することでしかない。〈読まれるべき言葉〉がどのような言葉であるかは時代によって異なるであろうが、それにもかかわらず、どの時代にも、引きつがれて〈読まれるべき言葉〉がある。そして、それを読みつぐのが文化なのである。
ゆえに、〈読まれるべき言葉〉を読みつぐのを教えないことが、究極的には、文化の否定というイデオロギーにつながるのである。文化の否定というイデオロギーのそもそもの種は近代西洋のユートピア主義にあり、それは、原始共産制礼賛、文化的資産を持つ者と持たざる者との差をなくそうとするポピュリズム、社会の規範からまったく自由な〈主体〉の物象化など、さまざまな形をとって、西洋でも文化の破壊を招いてきた。だが、非西洋においての文化の破壊は、西洋とは比較にならないすさまじいものとなった。中国の文化大革命は貴重な文化財の多くを地球から永遠に消し去り、読書人を吊し上げて辱めた。カソボジアのクメール・ルージュにいたっては読書人をすべからく虐殺した。日本の戦後五十年の国語教育を、文化大革命令クメール・ルージュと比べようというわけではない。もともと文学好きの日本人である。国語教育を通じて優れた文学を子供たちに読ませる努力は戦後も続き、優れた文学に親しんだ人たちが育ち、一時期はこの世の春とばかり文学は栄えた。作家たちは殺されるどころか「文化人」の代表として大きな顔をしていられた。作家によっては羨ましいほどの大金持にもなった。だが、目本の国語教育の理想を、〈読まれるべき言葉〉を読む国民を育てるところに設定しなかった――すなわち、文化を継承するところに設定しなかったがゆえに、時を経るに従い、しだいしだいに〈読まれるべき言葉〉が読みつがれなくなっていったのである。〈読まれるべき言葉〉を読みつなぐのを理想としない教育の意味をあえて極限まで突き進めれば、それはやはり文化の否定と言わざるをえない。
文化は国家のものでもなければ、権力者のものでもない。私たち人間のものである。だから、難民が自分の国を追われても、何とかして自分たちの〈読まれるべき言葉〉を継承していこうとするのである。「さまよえるユダヤ人」にいたっては、国が亡ぼされたあと実に二千五百年にわたって世界中を流浪しながらも嵩張る教典だけは宝物のように抱えて読みつぎ、自分たちの文化を継承してきた。
中国の文化大革命は一党独裁のもとでおこったことである。クメール・ルージュの虐殺も長年にわたる植民地支配、それに続いた腐敗政権、さらにはヴェトナム戦争の波及効果のせいでおこったことである。しかし、日本は戦後五十年のあいだ、平和と繁栄と言論の自由を享受しつつ、知らず知らずのうちに自らの手で日本語の〈読まれるべき言葉〉を読まない世代を育てていったのである。〈書き言葉〉の本質が読むことにあるのを否定し、ついには教科書から漱石や鴎外を追い出そうとまでしたのである。そして、誰にでも読めるだけでなく、誰にでも書けるような文章を教科書に載せるという馬鹿げたことをするようになったのであった。
〈国語〉など自然に学べるものだとしか日本人が思わなくなって当然であった。〈書く主体〉としての自己表出が〈文学〉だと日本人が思うようになって当然であった。〈国語イデオロギー〉がもっとも幼稚な形で跋扈するようになって当然であった。
そして、あの懐かしい「文語体」の数々の詩歌。
「西洋の衝撃」を受けたあとも、「文語体」は明治後期から大正、さらには昭和のほんとうの初期にかけ、詩歌のなかで絢爛と花ひらいていった。そして、翻訳詩も含めて、日本近代文学をより豊かなものにしていった。その「文語体」という文字文化さえ、戦後から歳月を経るうちに、日本の国語教育は、過去へ過去へと次第に追いやりつつあるのである。
からまつの林を過ぎて、
からまつをしみじみと見き。
からまつはさびしかりけり。
たびゆくはさびしかりけり。(『落葉松』北原白秋)
「文語体」を過去へと追いやるうちに、若い世代の日本人は、「文語体」で書かれた詩歌を読む習慣さえ失っていった。
しみじみと、さびしかりけり。
ひたぶるに、さびしかりけり。
しかも、日本語という特異な〈書き言葉〉をもつ私たち日本人こそ、世界に向かい、まさに誰よりも声を大にして、「表音主義」を批判すべきだったのである。
日本語は〈話し言葉〉としては特別な言葉ではない。
だが、その〈書き言葉〉は、世にも特異な表記法をもつ。日本語は、朝鮮語が一時そうしていたように、漢字という表意文字と、自分たちの表音文字を混ぜて書く。それだけでも特異なのに、日本語にはなんと二種類の表音文字―「ひらがな」と「カタカナ」―がある。そのうえ、漢字そのものを「音読み」と「訓読み」という二種類の読みかたをする。しかもその「音読み」も「訓読み」も複雑なことこのうえない。<中略>スティーヴン・ロジャー・フィッシャーという言語学者は『文字の歴史』という本のなかで、「日本語は、これまで地球上に存在した文字のなかで最も複雑な文字によって表記される」とし、その日本語の表記法の複雑さを、数頁にわたって―「重箱読み」や「湯桶読み」にまで言及して―説明しようと試みるが、日本語を知らない読者が読んだら、絶句し、たぶん途中で読むのをあきらめるであろう。
だが、そのような表記法をもつ〈書き言葉〉が地球上に存在するというその事実そのものが、「表音主義」の批判となるのである。
それは、日本語が視覚に訴える言葉だからではない。表音文字でさえも多かれ少なかれ視覚に訴える。モスクの正面を飾るアラビア文字は、絵のように美しく厳かである。ヒンディー語に使われるデーヴァナーガリー文字も、絵のように美しく遊び心を感じさせる。ローマ字アルファベットといえども、視覚的な側面を残しており、コンピューターで作成する文字でさえさまざまなフォントが使われるのはそのせいである。古典的なフォントと近代的なフォントを使い分けることによって、同じ文章が、古風にもモダンにも感じられる。視覚的効果が意味の生産と関係するというのは、どの文字でもありうることなのである。
だが、表記法を使い分けるのが意味の生産にかかわるというのは、それとは別のレベルの話で、日本語独特のことである。そのようなことは、漢字という表意文字を使う漢文でもおこらない。表記法を使い分けることによって生まれる意味のちがいとは、一本の筆で、溜息が出るほど流麗な達筆で書かれていようと、一本のボールペンで、これまた思わず嘆息するほどまずい字で書かれていようと、あるいは、明朝体が使われていようと、ゴシック体が使われていようと、そのような視覚的な差とはまったく関係のないところから生まれる、意味のちがいである。
同じ音をした同じ言葉―それを異なった文字で表すところから生まれる、意味のちがいである。
ふらんすへ行きたしと思へども
ふらんすはあまりに遠し
せめては新しき背広をきて
きままなる旅にいでてみん。
という例の萩原朔太郎の詩も、最初の二行を
仏蘭西へ行きたしと思へども
仏蘭西はあまりに遠し
に変えてしまうと、朔太郎の詩のなよなよと頼りなげな詩情が消えてしまう。
フランスヘ行きたしと思へども
フランスはあまりに遠し
となると、あたりまえの心情をあたりまえに訴えているだけになってしまう。だが、右(上)のような差は、日本語を知らない人にはわかりえない。 <傍線は引用者による>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
そこで、「<読まれるべき言葉>を読む国民を育てるところに設定しなかった」ということを「演劇」に置き換えると、どんな問題になるのか?
それは明白だが、演劇を教育の枠の中に入れなかったことである。「文化」を継承する国民を意図的に育てなかったことでもある。
演劇において、<読まれるべき言葉>とは紛れもなく作家の「台本」であり、役者の「からだ」である。そしてさらに、演劇固有の特色としては「せりふ」を発することが現象面での行為だが、優れた表現者の発する「せりふ」は観客にとって「読まれるべき言葉」でもある。観客は「話し言葉」を「聞き」ながら「読まれるべき言葉」を「読ん」でいるのである。
ヨーロッパリアリズム演劇の伝統を日本に取り込もうとした近代演劇の流れと、日本固有の能や歌舞伎の伝統とが相容れない問題をここで含んでしまったことについては深入りしないが、よるべき規範が2つ以上存在する「日本近代演劇」はここで、多様性を宿命づけられていると言える。
高校演劇につてもこの問題から自由ではないが、いわゆる大衆性と、芸術性、笑いとシリアス、リアリズムと前衛風、等々……、更にそこに舞踊と舞踏、ダンスなどと身体性が絡む。
しかし「高校演劇」と言うジャンルに囚われることだけはしたくないと、ずーっと思ってきた。
東近江市立湖東第三小学校 地域コーディネーター
黄地 伸